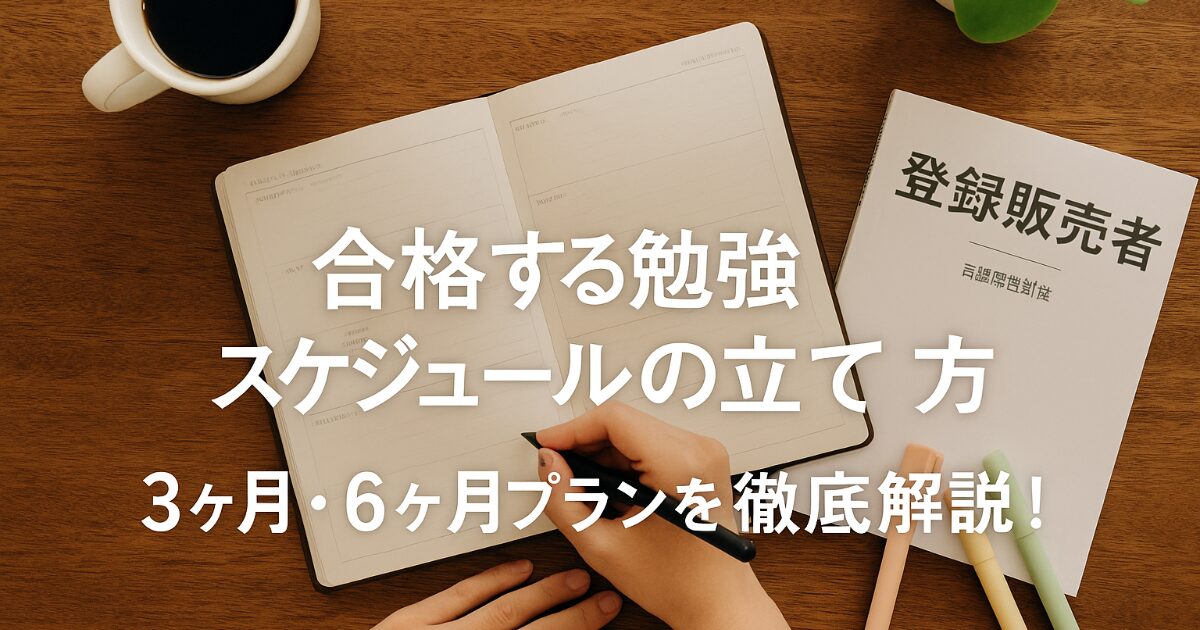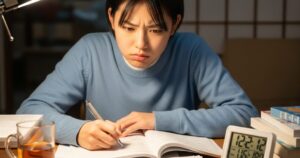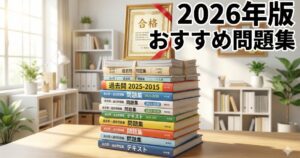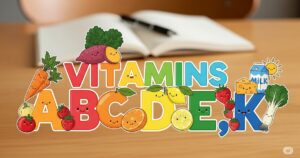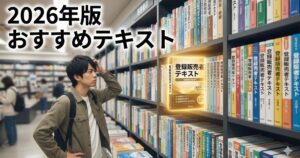「登録販売者の資格を取りたいけど、いつから勉強を始めればいいの?」 「3ヶ月で合格できる? それとも、もっと時間をかけるべき?」
いざ勉強を始めようと思っても、最初に悩むのが「いつから、どのように計画を立てるか」ですよね。分厚いテキストを前に、途方に暮れてしまう気持ち、非常によく分かります。
この記事では、そんなあなたのために、登録販売者試験に合格するための、正しい勉強スケジュールの立て方を徹底解説します。3ヶ月プランと6ヶ月プランの具体的な例を挙げながら、あなたのライフスタイルに合った計画を見つけるお手伝いをします。
なぜ勉強スケジュールの作成が合格への第一歩なのか?
効果的な計画を立てるには、まずゴールまでの距離と自分の現在地を知ることが不可欠です。
合格に必要な平均勉強時間は?(200〜300時間が目安)
一般的に、登録販売者試験の合格に必要な勉強時間は200〜300時間と言われています。もちろん、これは医療系の知識が全くない初学者の方を基準とした目安であり、個人の知識レベルによって変動します。
この時間を、あなたが確保できる日数で割ることで、1日あたりの必要な勉強時間が見えてきます。
- 6ヶ月(約180日)で合格を目指す場合: 1日あたり約1時間〜1時間半
- 3ヶ月(約90日)で合格を目指す場合: 1日あたり約2時間〜3時間半
まずはこの時間を意識して、「自分にはどのくらいの準備期間が合っているか」を考えてみましょう。
あなたはどっち?「コツコツ派」と「短期集中派」
ご自身の性格や確保できる時間に合わせて、どちらのタイプが向いているか自己診断してみましょう。
- コツコツ派: 毎日少しずつでも勉強を継続するのが得意な方。仕事や家事と両立したい方。
→ 「6ヶ月プラン」がおすすめ。 - 短期集中派: 一定期間、勉強に集中できる環境がある方。目標が近い方がモチベーションを維持しやすい方。
→ 「3ヶ月プラン」がおすすめ。
【合格者の声】勉強開始の「理想」と「現実」
📢【Aさん(20代・学生):3ヶ月の短期集中!でも、ギリギリでした】 「大学の夏休みを利用して、3ヶ月で一気に合格しました。毎日5〜6時間勉強する生活は大変でしたが、集中できたのは良かったです。ただ、正直かなりギリギリでした…。もしやり直せるなら、5月頃から少しずつ始めて、夏休みは復習と過去問演習に充てたかったです。」
📢【Bさん(40代・主婦):半年前から始めて、余裕の合格】 「子供が寝た後の1時間を、毎日の勉強時間に充てました。半年前から始めたので、焦ることなく、自分のペースで着実に進められたのが良かったです。試験直前期も、新しいことを覚えるのではなく、復習に集中できたので、当日は自信を持って臨めました。」
📢【Cさん(30代・会社員):2ヶ月前に始めて、数点足らずに不合格…】 「仕事が忙しい中、2ヶ月で詰め込もうとしましたが、急な残業などで計画が崩れ、消化不良のまま本番へ。結果は、あと数点で不合格でした。本当に悔しいです。『もっと早く、せめてあと1ヶ月早く始めていれば…』と痛感しました。」
多くの合格者は、試験日の3〜6ヶ月前から本格的に勉強をスタートしています。しかし、「もっと早く始めておけばよかった…」という後悔の声も少なくありません。
失敗しない!登録販売者 勉強スケジュール作成の3つの鉄則
具体的なプランに入る前に、どんな計画にも共通する、絶対に失敗しないための「3つの鉄則」を共有します。この心構えを持つだけで、あなたの計画の達成率は飛躍的に高まります。
鉄則①:無理な計画を立てない(継続が最優先)
最もよくある失敗が、「毎日3時間勉強する!」といった、最初からハードルが高すぎる計画を立ててしまうことです。計画は、1日でも達成できないと、途端にやる気が失せてしまいます。 大切なのは、完璧な計画より、「これなら、どんなに疲れていても続けられる」という、現実的な最低ラインの計画を立てることです。「毎日最低でも30分はテキストを開く」といったレベルで十分です。
鉄則②:タスクは「具体的」にする(行動を明確化)
「今日は3章を勉強する」といった、漠然とした計画はNGです。何をすれば終わりなのかが曖昧で、結局何も手につかないまま時間が過ぎてしまいます。 タスクは、「誰が聞いても、やるべきことが分かる」レベルまで具体的にしましょう。
- ダメな例: 「3章を勉強する」
- 良い例: 「3章のテキストp.50〜p.65を読み、対応する問題集を10問解く」
鉄則③:「予備日」を必ず設ける(修正できる余白を作る)
どんなに完璧な計画を立てても、急な残業や、家族の体調不良などで、計画通りに進まない日は必ずやってきます。 そんな時のために、週に1日、あるいは月に数日、「何もしない日」や「遅れを取り戻すための日」として、予備日(バッファ)をあらかじめ計画に組み込んでおきましょう。この「余白」があることで、計画が破綻するのを防ぎ、精神的な余裕を持って学習を続けられます。
【3ヶ月で合格】短期集中型!勉強スケジュールモデルプラン

【3ヶ月プラン】短期集中で一気に合格を目指すコース
勉強時間をしっかり確保できる方向けの、ハイペースなプランです。
- 1ヶ月目:全範囲の高速インプット&アウトプット
- 内容: 1週間で1〜2章のペースで、全範囲のテキストと講義動画(あれば)を高速で1周します。完璧に理解しようとせず、「全体像を掴む」ことを目標にします。各章を終えるごとに、すぐに該当範囲の問題集を解き、知識の定着を図ります。
- 内容: 1週間で1〜2章のペースで、全範囲のテキストと講義動画(あれば)を高速で1周します。完璧に理解しようとせず、「全体像を掴む」ことを目標にします。各章を終えるごとに、すぐに該当範囲の問題集を解き、知識の定着を図ります。
- 2ヶ月目:苦手分野の克服と3章の集中攻略
- 内容: 1ヶ月目の問題演習で明らかになった自分の苦手分野と、最難関の3章に全ての時間を注ぎます。特に3章は、この1ヶ月で徹底的に叩き込みます。
- 内容: 1ヶ月目の問題演習で明らかになった自分の苦手分野と、最難関の3章に全ての時間を注ぎます。特に3章は、この1ヶ月で徹底的に叩き込みます。
- 3ヶ月目:ひたすら過去問演習
- 内容: 6ヶ月プランの最終月と同様、過去問演習に全ての時間を費やします。週に2〜3年分の過去問を解くペースで進め、時間配分の感覚と実践的な解答能力を体に叩き込みます。
3ヶ月プラン 週別スケジュール例
| 週 | 学習内容(例) | 重点ポイント |
| 1-2週目 | 第1章(医薬品に共通する特性と基本的な知識) | 基礎用語の理解、重要項目の暗記 |
| 3-4週目 | 第2章(人体の構造と機能、及び疾病) | 図やイラストを活用し、体の仕組みを視覚的に理解 |
| 5-6週目 | 第3章(主な医薬品とその作用) | 医薬品の分類と作用機序を関連付けて覚える |
| 7-8週目 | 第4章(医薬品の適正使用と安全対策) | 法令や制度の内容を正確に理解 |
| 9-10週目 | 第5章(医薬品、医薬部外品及び化粧品に関する法規・制度) | 数値や期間など、細かい部分も確実に暗記 |
| 11-12週目 | 全範囲の総復習、過去問題集を解く | 苦手分野の克服、時間配分を意識した演習 |
【6ヶ月で合格】じっくり学ぶ!余裕を持った勉強スケジュールモデルプラン

【6ヶ月プラン】無理なく着実に知識を積み上げる王道コース
初学者の方に最もおすすめな、焦らずじっくりと知識を定着させるプランです。
- 1〜2ヶ月目:基礎固めフェーズ
- 内容: まずは第2章「人体の働きと医薬品」と第4章「薬事関係法規・制度」から始めます。
2章で体の仕組みを理解しておくことで、3章の薬の作用がスムーズに頭に入ってきます。
4章は暗記が中心ですが、後回しにすると手が回らなくなることが多いので、早めに着手するのが吉です。
この時期は、テキストを読み、各章末の問題を解くことを繰り返しましょう。
- 内容: まずは第2章「人体の働きと医薬品」と第4章「薬事関係法規・制度」から始めます。
- 3〜4ヶ月目:最難関の攻略フェーズ
- 内容: この2ヶ月間は、試験の合否を分ける第3章「主な医薬品とその作用」に集中します。
範囲が広いため、焦らず「かぜ薬とその成分」「胃腸薬とその成分」といったように、薬効群ごとにブロック分けして、一つひとつ確実に覚えていきましょう。
インプットとアウトプットの比率は「4:6」を意識し、問題演習に多くの時間を割きます。
- 内容: この2ヶ月間は、試験の合否を分ける第3章「主な医薬品とその作用」に集中します。
- 5ヶ月目:残りのインプットと総復習フェーズ
- 内容: 比較的暗記量の少ない第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」と第5章「医薬品の適正使用・安全対策」をインプットします。同時に、これまで学んだ2章・3章・4章の総復習を行い、知識の穴を埋めていきます。
- 内容: 比較的暗記量の少ない第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」と第5章「医薬品の適正使用・安全対策」をインプットします。同時に、これまで学んだ2章・3章・4章の総復習を行い、知識の穴を埋めていきます。
- 6ヶ月目:実践力アップフェーズ
- 内容: とにかく過去問演習に徹します。最低でも過去3〜5年分を、時間を計って本番さながらに解きましょう。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを必ずテキストに戻って確認します。
これを3周繰り返せば、合格は目前です。
- 内容: とにかく過去問演習に徹します。最低でも過去3〜5年分を、時間を計って本番さながらに解きましょう。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを必ずテキストに戻って確認します。
6ヶ月プラン 月別スケジュール例
| 月 | 学習内容(例) | 重点ポイント |
| 1ヶ月目 | 第1章 | 基礎をじっくり理解 |
| 2ヶ月目 | 第2章 | 図解で視覚的に学ぶ |
| 3ヶ月目 | 第3章 | 作用機序を関連付け |
| 4ヶ月目 | 第4章 | 法令・制度を正確に |
| 5ヶ月目 | 第5章 | 細かい部分も暗記 |
| 6ヶ月目 | 全範囲復習+過去問演習 | 弱点克服と実践力養成 |
合格者が語る!勉強開始時期と後悔したこと

🗣️【合格者Aさん(30代・女性)】「私は試験の3ヶ月前に勉強を始めたんですが、特に法規が覚えきれなくて、直前は睡眠時間を削るほど必死でした。もっと早く、せめて半年前から始めておけば、焦らずに済んだのに…と後悔しています。」
🗣️【合格者Bさん(40代・男性)】*「6ヶ月前から計画的に勉強を進めたおかげで、余裕を持って合格できました。ただ、最初の1ヶ月は基礎固めに時間をかけすぎたかもしれません。過去問にもっと早くから触れておけば、効率が上がったと思います。」
ライフスタイル別・毎日の勉強時間の作り方

「計画は立てたけど、実行する時間がない…」そんな方のために、具体的な時間の捻出方法をご紹介します。
社会人(フルタイム勤務)の場合
- 通勤時間: 電車やバスの中は、スマホアプリでの一問一答や、動画・音声講義での「耳学」に最適な時間です。
- お昼休み: 食後の15分〜30分を勉強時間に充てましょう。テキストの数ページを読む、単語カードを見返すなど、短い時間でも毎日続ければ大きな力になります。
- 寝る前の30分: スマホを置いて、その日学んだことの復習や、テキストの読み込みに使いましょう。記憶が定着しやすいゴールデンタイムです。
主婦・主夫(子育て中)の場合
- 子供が学校や昼寝中の時間: 最も集中できる貴重な時間です。タイマーをセットし、「この時間は勉強する」と決めて取り組みましょう。
- 家事をしながらの「ながら聴き」: 料理や洗濯をしながら、イヤホンで講義動画を音声だけで聴くのも非常に効果的です。
- 家族の協力: 「週末の1時間だけ、集中させてほしい」と家族にお願いし、協力体制を築くことも大切です。
挫折しないための進捗管理とモチベーション維持術

最後に、長い勉強期間を乗り越えるためのコツです。
計画は「見える化」する
手帳やカレンダーアプリに、その日にやるべきことを書き出しましょう。達成できたらチェックを入れることで、自分の頑張りが可視化され、モチベーションに繋がります。
完璧を目指さない
計画通りに進まない日があっても、自分を責めないでください。「今日は疲れているから、一問一答を10問だけやろう」など、ハードルを下げることが継続の秘訣です。「やらない日」があっても、次の日にまた再開すれば良いのです。
SNSで勉強仲間を見つける
X(旧Twitter)などで「#登録販売者試験」「#勉強垢」と検索すれば、たくさんの仲間が見つかります。お互いの進捗を報告し合ったり、励まし合ったりすることで、孤独な勉強も乗り越えやすくなります。
小さなご褒美を設定する
「この章を終えたら、好きなケーキを食べる」「過去問で合格点を取れたら、週末は好きな映画を見る」など、小さなご褒美を設定すると、ゲーム感覚で楽しく学習を進められます。
まとめ:最高の勉強スケジュールは、今日、あなたが始めること
登録販売者試験に合格するための、勉強スケジュールの立て方について解説しました。
- まず、合格に必要な総勉強時間(約200〜300時間)を把握する。
- 自分の生活スタイルに合わせて「6ヶ月プラン」か「3ヶ月プラン」かを選ぶ。
- 通勤時間や家事の合間など、スキマ時間を徹底的に活用する。
- 完璧を目指さず、モチベーションを維持する工夫を取り入れる。
最も大切なのは、この記事で紹介したモデルプランを参考に、あなただけのオリジナルスケジュールを組み立てることです。それが、あなたにとっての合格への最短距離となります。
この「学習計画」は、合格への羅針盤です。
そして、羅針盤が指し示す道を効率よく進むためには、質の高い「地図(教材)」や、時には「乗り物(通信講座)」も必要になります。
具体的な勉強のテクニックや、おすすめの講座については、以下の記事もぜひ参考にしてください。
・最難関!第3章の具体的な暗記術を知りたい方へ → 【挫折ポイントを完全攻略】登録販売者 第3章の効率的な覚え方…
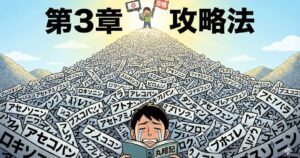
正直、独学だけで合格できるか不安…という方へ
「仕事や家事で忙しくて、勉強時間が取れない…」
「もし今年落ちたら、また1年勉強し直しになるのは辛い…」
そんな不安がある方は、独学にこだわる前に「通信講座」を検討してみてください。
最近はスマホだけで学べる講座や、独学と変わらない費用で受講できる格安講座も増えています。
「今年絶対に合格したい!」という方は、自分に合った講座がないか、まずはチェックしてみましょう。